記事一覧
ブログ | ポスト・ヒューマン・ジャパン株式会社 | 社会福祉 介護事業 コンサル
-
ブログ2023.10.30
リーダーの失言、リーダーに苦言?
いつもお世話になっております。
PHJの堀内です。

先週は、行政の長の失言、連発、そして、
リーダーの資質について、「身内からの苦言」が話題でしたね。
自民党の世耕弘成参院幹事長は、岸田文雄首相の所信表明に対する代表質問を行った際、首相の政治姿勢やリーダーの資質、発信のあり方について、首相に批判まじりのダメ出し、苦言を連発とか。
世耕氏は「(国民に)なぜ評価されないのだろうというのが、率直なご心境ではないか」と指摘。
「支持率が向上しない最大の原因は、国民が期待するリーダーとしての姿が示せていないからではないか」と断言。
世耕氏自身が考えるリーダー像を「決断し、その内容をわかりやすい言葉で伝えて人を動かし、その結果について責任を取る。しかし残念ながら、岸田総理の決断と言葉について、いくばくかの弱さを感じざるを得ない」とも。
また、「総理は国民への発信方法に心を砕いておられる」とした上で「綸言(りんげん)汗のごとし」という格言を引き合いに「リーダーの発した言葉は、かいた汗のように元に戻すことはできない」とも訴えたとか。
さて、リーダーとはどうあるべきか。
「リーダーに関する唯一の定義は、つき従う者がいるということである」
ピーター・ドラッカー氏『プロフェッショナルの条件――いかに成果をあげ、成長するか』から
この「つき従う者」とは、強制的に従わせられた者ではなく、「そのリーダーを信頼し、自らの意志に基づいて従う者」を意味しています。つまり、リーダーとは「誰かから信頼されている」ことが必然だと、ピーター・ドラッカー氏は説いているのです。
リーダーとして役割を果たすためには、さまざまな要素が求められますが、ピーター・ドラッカー氏によるリーダーとなる人材に求められる9つの条件をご紹介しましょう。
・メンバーの強みを見抜き、成果につなげる「観察力」
・方向性やビジョンを伝える「発信力」
・変化に対応できる「柔軟性」
・相手との関係性を構築する「コミュニケーションスキル」
・自分の価値観や軸に基づく「決断力」
・一歩先の未来も想像しながらアクションする「行動力」
・最後に踏ん張れる「業務遂行能力」
・チーム全体の責任を背負える「責任感」
・メンバーを育成しリーダーを増やす「育成能力」
介護業界の経営者の皆様!
支持率を気にして対策をとるけれど、国民から信頼されない岸田総理の姿は、
「科学的介護を推進したが、現場が納得しない」と、ご発言される経営者様の姿と同じです。
「職員が期待するリーダーとしての姿が示せていないから」
「決断し、その内容をわかりやすい言葉で伝えて人を動かし、その結果について責任を取るという姿勢がないから」
まさしく、これです。
結論
科学的介護の推進は、「現場が反対するからできない」ではない。
経営者のリーダーとしての資質に問題があるからできないのです。
その資質の無いリーダーは退場という時代でしょうか。
生意気な発言。ごめんなさい。これは、失言?苦言?
-
ブログ2023.10.27
1on1フィードバックミーティングはなぜ重要なのか
みなさん、お元気ですか?
経営者としての、施設長としての、管理者としての、本日1日のあなたの仕事の「意図」はどのようなものでしょうか?
ポスト・ヒューマン・ジャパン株式会社(PHJ)の谷本です。

弊社PHJの提供する「科学的介護マネジメントシステム」の構築支援では、必ず
社会福祉法人様の組織の仕組みとして、1on1フィードバックミーティングの導入をお願いしています。
理事長からはじまって、直上上司と直下部下との1対1で短時間で実施して頂くものです。
頻度は、月3回必須!
これ、とっても重要です!
しかし、多くの社会福祉法人様は、この1on1フィードバックミーティングの完全実施事態に苦労します。
見事な「言い訳」を駆使して、「実施できない理由」を創造して、やり過ごそうとします。
しかし、それを許してはいけません。
月3回の1on1フィードバックミーティング実施の工夫もできない組織が「科学的介護」でアウトカムを実現し、利用者・入居者を幸せにすることなどできるわけがないのです。
「甘え」を排することがリーダーの、マネジメント職の責任と役割です。
なぜ、1on1フィードバックミーティングが重要なのか?
それは、
1on1(ワンオンワン)フィードバックミーティングは、マネージメントと従業員間のコミュニケーションと関係を強化するためのものだからです。
以下は、その具体的な理由です。
-
1.オープンなコミュニケーション: 1on1の環境は、従業員が気軽に意見や懸念を共有できる場です。
これにより、マネージャーは従業員のニーズを理解し、それに対応することができます。 -
2.問題の早期発見と解決: 小さな問題が大きな問題に発展する前に、早期に対処できます。
-
3.パーソナルな成長とキャリア開発: 1on1ミーティングでは、個々のパフォーマンスや成長目標に
対するフィードバックが行いやすいです。 -
4.従業員のモチベーション向上: 正確かつ具体的なフィードバックを提供することで、従業員の自己
効力感が向上します。 -
5.信頼関係の構築: 定期的な1on1ミーティングを通じて、従業員とマネージャーの信頼関係が築かれ、
長期的な成功につながります。 -
6.戦略的な方向性: 従業員との1on1ミーティングを通じて、チームやプロジェクトの戦略的な方向性
についても議論することができます。 -
7.文化と価値観の共有: 企業文化や価値観をより効果的に伝え、共有することができます。
-
8.タスクと優先順位の明確化: 従業員自身も、自分の仕事の優先順位や期待値をよく理解することができます。
-
9.フィードバックループの高速化: 1on1は即時性があり、フィードバックループを高速化できるので、
改善が早く行えます -
10.全体の生産性向上: 上記のすべての要素が結合することで、チーム全体の生産性と働きがいが向上します。
以上のような理由から、1on1フィードバックミーティングは組織にとって非常に価値のある活動とされています。
離職率低下の最大化のためにも、
心理的安全性の確保のためにも、
ぜひ、1on1フィードバックミーティングの実施を死守しましょう。
では、また!
-
-
ブログ2023.10.26
介護就労者、初の減少〜日経新聞1面で報じる
みなさん、お元気ですか?
経営者としての、施設長としての、管理者としての、本日1日のあなたの仕事の「意図」はどのようなものでしょうか?
ポスト・ヒューマン・ジャパン株式会社(PHJ)の谷本です。
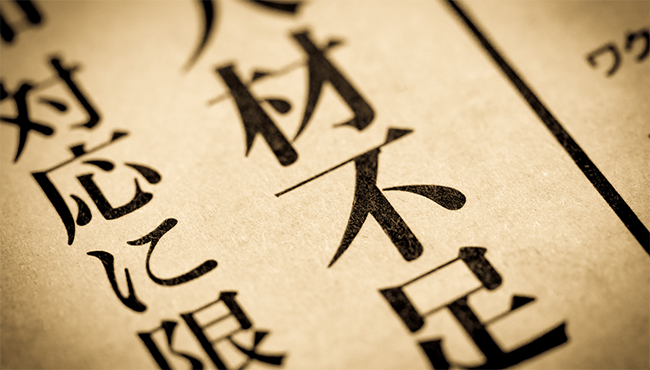
2023年10月23日(月)朝刊一面に日本経済新聞が掲載した記事が、「介護業界から人材が流出している」という内容のものでした。
厚生労働省の分析によると2022年は離職した人が新たに働き始めた人を上回り、就労者が前年より1.6%減ったとこのと。
飲食・小売りや製造業などで賃上げが広がり、より良い待遇を求めて転職する人が増えたらしいのです。
介護を必要とする高齢者は増えており、処遇の改善による介護士の確保が急務になるとしました。
実は、今後多くの業界で、人材不足が通常モードとなるのが日本の現実です。
そのため、この悩みは未来永劫継続することになります。
いわば、「当たり前」の話というわけです。
人材の溢れていた頃のことを、我々は「人材バブル期」と表現することになるでしょう。
ですから、特養など介護現場で「人が足りないのに科学的介護なんて・・・」という声が上がったら、経営者は上手に伝えましょう。
「足りないというより、今が通常モードですよ〜!」。
ちなみに、「科学的介護」をユニットケアの特養で行う場合の通常モードは日中1ユニット10人に対して一人の介護職で普通に実施します。
どうやるか?やっている特養は「それが普通ですよ」とおっしゃいます。
人生も、仕事も、「何が普通」「何が通常か」は、99%思い込みの世界です。
業界別では正社員の不足について、帝国データバンクの調べ〜
「人手不足に対する企業の動向調査(2023年1月)」
では、
①旅館・ホテル
②情報サービス
③メンテナンス・警備
④建設
⑤人材派遣・紹介
⑥自動車・同部品小売
⑦金融
⑧運輸・物流
⑨飲食店
⑩医療・福祉・保健衛生
の順番で人手不足感が強いとのこと。
これからは、これらの業種のうち、おそらく
①旅館・ホテル
③メンテナンス・警備
④建設
⑧運輸・物流
⑨飲食店
との人材の取り合いになるでしょう。
今の政府のムードでは賃金で革命的な待遇にしない限り、他業種に賃金面で
遠く引き離される可能性もあります。
しかし、革命的・・・は日本人が最も苦手科目。
待遇面を超えた、介護という業種のブランディングが必要となります。
その鍵が「科学的介護」です。
そろそろ学びを始めませんか?
では、また!
-
ブログ2023.10.25
小規模多機能型居宅介護における2024年介護報酬改定における論点から
みなさん、お元気ですか?
経営者としての、施設長としての、管理者としての、本日1日のあなたの仕事の「意図」はどのようなものでしょうか?
ポスト・ヒューマン・ジャパン株式会社(PHJ)の谷本です。
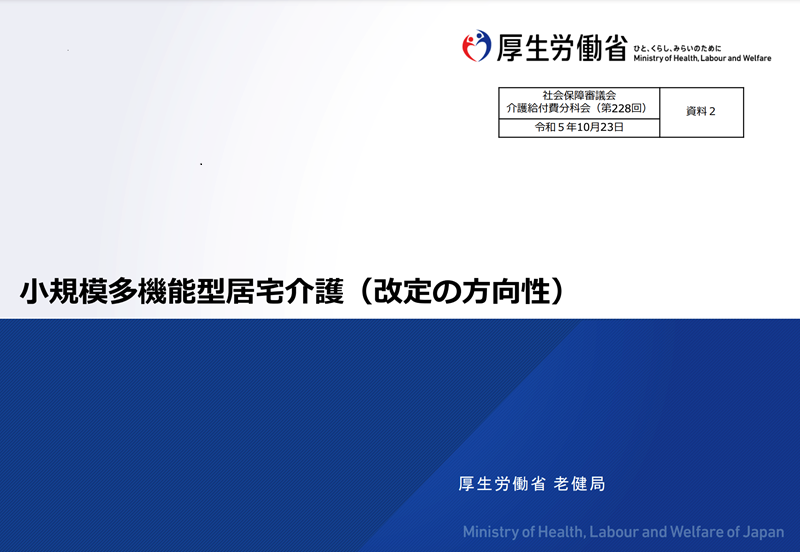
令和5年10月23日(月)に開催された厚生労働省社会保障審議会介護給付費分科会で、小規模多機能型居宅介護について議論が行われました。
注目すべきは、認知症高齢者への対応です。
論点①
◼ 平成21年度介護報酬改定において、小規模多機能型居宅介護の利用者ニーズに対応するため、認知症高齢者等への対応に対する評価として、認知症加算を創設したところ。
◼ 認知症加算の算定率(※)は事業所ベースで、(Ⅰ)92.3%(39.5%:利用者ベース)、(Ⅱ)70.5%(9.3%:利用者ベース)と 多くの事業所が算定を行っている。 ※ 介護給付費等実態統計(令和4年4月審査分)(利用者ベースについては、老健局認知症施策・地域介護推進課にて算出)
◼ また、小規模多機能型居宅介護は、中重度の要介護状態となっても住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、24時間365 日の在宅生活を支援するサービスとして、その機能・役割を果たしてきたところであり、近年サービス利用者のうち認知症高齢者の割合は増加傾向にある。
◼ 他方、認知症の重度化や家族介護の負担増加により、サービス利用を終了する利用者も一定数いる状況。
◼ こうした状況を踏まえ、小規模多機能型居宅介護における認知症対応力を更に強化していくために、どのような対応が考えられるか。
◼ 小規模多機能型居宅介護の利用者における認知症高齢者の割合が増加傾向にある中で、認知症が重度化した際には、施設・居住系 サービスへ移行している状況であることを踏まえ、サービスに期待される機能・役割を強化していく必要がある。
◼ このため、認知症対応力の更なる強化を図る観点から、現行の認知症加算の取組に加えて、認知症ケアに関する専門的研修修了者の配置や認知症ケアの指導、研修の実施等を行っていることについて新たに評価することとしてはどうか。
※ 看護小規模多機能型居宅介護も同様にしてはどうか。
◼ また、新設する区分の取組を促す観点から、現行の単位数は見直してはどうか。
という内容。
さて、認知症高齢者への対応として〜現行の認知症加算の取組に加えて、認知症ケアに関する専門的研修修了者の配置や認知症ケアの指導、研修の実施等を行っていることについて新たに評価すること・・・・となっていますが、専門的研修の内容は?というかどのような認知症ケアスキルが身につくのか?
↓
認知症患者の行動の変化や感情の波に対処する方法について、安全かつ適切なサポートスキルを磨くための一般的なアプローチを以下に示します:
- 1. 情報の収集と理解:
- ・認知症患者のケアを提供する前に、その患者に関する情報を収集し、彼らの背景、好み、特異なニーズを理解します。これにより、個別化されたアプローチを開発しやすくなります。
- 2. 穏やかなコミュニケーション:
- ・認知症患者とのコミュニケーションは穏やかで非常に重要です。言葉だけでなく、非言語的なコミュニケーション(表情、ジェスチャー、姿勢など)も活用しましょう。感情や不安に対して理解と共感を示します。
- 3. リダイレクト技巧:
- ・認知症患者が不安や混乱している場合、その気持ちを軽減するためにリダイレクト技巧を使用できます。例えば、話題を変えることや、患者が好きなことについて話すことで気分転換を図ります。
- 4. ストレス軽減:
- ・認知症患者のストレスを軽減するために、静かで安心感のある環境を提供しましょう。過度の刺激や騒音を避け、リラックスできる状況を整えます。
- 5. 日常のルーチン:
- ・認知症患者には予測可能な日常のルーチンが重要です。毎日同じ時間に食事をとる、同じ活動を行うなど、安心感を提供することが役立ちます。
- 6. 協力体制の構築:
- ・認知症患者のケアは単独で行うのではなく、協力体制を築くことが重要です。家族、介護者、医療専門家と連携し、緊急の場合に適切な対応を取る計画を立てます。
- 7. 安全対策:
- ・認知症患者が自分や他人に危害を加える可能性がある場合、安全対策が必要です。これには、環境の安全性を確保する、必要に応じて監視を行う、誤飲や転倒の予防策を講じるなどが含まれます。
- 8. 感情の受容:
- ・認知症患者の感情を受容し、否定せずに対処することが大切です。感情を表現する機会を提供し、ストレスや不安を軽減する手助けをします。
これらのアプローチを組み合わせて、認知症患者の行動の変化や感情の波に適切に対処するスキルを磨くことができます。ただし、認知症の種類や進行度に応じて、個別のアプローチが必要となることもあります。また、研修プログラムでは具体的なケーススタディや役割演技を通じて実践的なスキルの向上も重要です。
フォームの始まり
このような内容であることはご存知の方も多いはず。フォームの終わり
しかし、これだけでは足りない。
認知症BPSD(行動心理・症状)や中核症状、それらを消失・緩和するにはさらなる教育と実践のPDCAが必要です。
PHJががっちり指導致します。
お気軽にお問い合わせください。
では、また!
- 1. 情報の収集と理解:
-
ブログ2023.10.24
認知症介護の救世主に!
いつもお世話になっております。
PHJの堀内です。

最近、ネットニュースなどで、認知症に関する話題が多いと感じています。
「家の中が便まみれに…「罪にならないなら母を捨てたい」認知症ケアを15年続ける女性の叫び 親の介護から逃げてはダメ?」
「介護している親を姥捨山に捨てていいって法律作るか、国が責任もって引き受けるかしてください」
「親に手を上げてしまった。もう在宅は限界なのかも」
SNSでは、という訴えが。
週刊現代の記事では、
「待機老人」が激増…老人ホームに入れない「認知症患者」が「精神病院」に送り込まれる
という見出しで。
いま日本全国で、認知症患者が精神科病院に入院するケースが増えている。厚生労働省の調査によれば、精神科病院に入院している患者数は、約25万9000人。実は、そのうち約7万3000人が認知症患者と。
特別養護老人ホームの場合、2022年4月の段階で、27万5000人が「待機」しているとのデータがある。認知症患者が精神科病院に送り込まれる背景には、認知症患者が老人ホームなどの施設に思った以上に入れない事情があるという。
また施設の側にとっても、認知症患者のケアは専門的な知識・技能が必要だったり、施設内で他の入居者と動線を分けたりしないといけないので、ハードルが高いと。
SNSでの訴えは、認知症の介護をしている方の悲鳴とも言えるでしょうね。
私も、認知症の母を介護した経験から他人事とは思えません。
「認知症患者のケアは専門的な知識・技能が必要」。
その通りです。
ですが、その理論と方法があります。
PHJが推進する「自立支援介護学」を使った「認知症症状消失」コーチングです。
「認知症あんしん生活実践ケア研究会」として、現在は、3期となっています。
研究会では、認知症症状消失の結果が出ています。
そして、その研究会は、「科学的介護AtoZ研究会」と名称変更し、
さらに、多くの企業・法人の皆様に、その学びの場をご提供したいと
考えています。
介護業界の経営者の皆様!
深刻な認知症患者ケアの救世主になっていただけませんか。
ヤフーニュースでは、こんな記事が、
施設に預けた結果、母親の体調が良くなり、笑顔も取り戻したという。
「認知症になってしまった親は、子どもからすると見るだけでつらい。“こうあってほしくない”“自分もこうなるのか”というどす黒い感情がどんどん湧いてくる。私の場合は遠距離だったので、否応なく施設に預けたのだが、結果として親が明るくなり、気持ちが安定してきた。生き返ったと言うと大げさかもしれないが、生き生きとしている。(中略)今日も帰省して会って来たが、ニコニコして『今本当に幸せ』みたいなことを言う。」と。
素晴らしい施設ですね。
これこそ介護のプロです。
皆様も、このような事業所、施設になっていただきたいです。
また、このような事業所、施設が、今、求められています。
