ブログ
ブログ|ポスト・ヒューマン・ジャパン株式会社(PHJ)
-
ブログ2024.01.09
「声」のチカラ
いつもお世話になっております。
PHJの堀内です。
今年もよろしくお願いいたします。
能登半島地震で、お亡くなりになられた方々に、心からお悔やみ申し上げます。
また、被災している方々に、心からお見舞い申し上げます。

1日、地震の情報の直後に、NHKを視ました。
「ここは大丈夫だとは思うのは危険です。情報を待って逃げ遅れないでください!」
「テレビを消さなくていいです!可能な限り逃げてください。高いところへ逃げること!」
「今すぐ避難!今すぐ避難!東日本大震災を思い出してください!」
緊迫した様子で、被災地へ何度も、非常事態であることを強く訴えるアナウンサーの声。
これは、11年に起きた東日本大震災を受け「命を守るための呼びかけ」について、
・確実に伝わること
・行動を促すこと
・予断を与えないこと
との思いであったと。
特に「自分だけは大丈夫」との思い込みを打ち破るための報道であったとか。
緊迫した声に、「命を守るため」との思いを感じました。
2日、日航機と海上保安庁の航空機が衝突した事故のニュース。
大惨事が予想されました。
その後、炎上した日航機から乗客乗員379人全員が無事に脱出との報道に、安堵したのは、皆さんも一緒だと思います。
欧米各紙が、事故を伝える記事の見出しには「ミラクル」という言葉が。
英ガーディアン紙は、「まず第一に、私たちは奇跡を目撃したと言わなければならない。あの飛行機から乗客全員を降ろした方法は、ほとんど信じられないほどだ」と、元民間パイロットの談話を。
米ニューヨーク・タイムズ紙は、旅客機の安全教育の専門家の話として「驚くべきだ。CAたちの反応速度は目を見張るものがあった。本当に奇跡だった」と。
また、ロイター通信は、「CAたちは素晴らしい仕事をしたに違いない。乗客全員が降りられたのは奇跡的だった」との航空分析会社の専門家の話を。
ここで注目されているのが「90秒ルール」。
航空界の「90秒ルール」と呼ばれる世界基準。
アメリカ連邦航空局(FAA)が、1967年に航空機メーカーに出した要件で、44席以上の旅客機についてはいずれの機種でも特定の条件下で90秒以内に全員が脱出できることを実証しなければならないというもの。
90秒ルールを満たしていると示すために、航空機メーカーは実際の機体を使って緊急脱出ができると実証するか、試験と分析を組み合わせて実証するかのいずれかの方法を用いなければならないという。
JALもこの基準にのっとって訓練しているとされ、今回、すべての乗客の命を救う結果になったという。
日頃の訓練の重要性を再確認するとともに、アナウンサー、CAの方々の「命を守る」プロの言動に称賛を贈りたいと思います。
2024年、「命を守る」声、「励まし」の声を広げて行くことが大切であることを痛感した年頭でした。
-
ブログ2023.12.26
認知症リスクの低減は?
いつもお世話になっております。
PHJの堀内です。

厚生労働省のデータによれば、2022年9月1日時点で100歳を超えた人は全国で9万526人(そのうち89%は女性)、52年連続で過去最多を更新中。
そこで、課題となるのが、「認知症」。
アルツハイマー協会が先月公開したジャーナル「アルツハイマーと認知症」に掲載されたメタ分析から、特定の性格特性と認知症のリスクとの間に関連性があることが明らかになったと。
研究者たちは、認知症の診断と性格の5大特性(協調性、解放性、外向性、誠実性、神経質傾向)を比較。また、ポジティブな感情(喜び、熱意、自信など)をより多く持つ人たちと、ネガティブな感情(怒り、緊張、恐怖など)をより多く持つ人たちの診断も比較。
ニューヨーク大学の医療研究施設ランゴーンヘルスで神経学の臨床助教授を務めるジョエル・サリナス医師は、神経質の度合いが高くネガティブな感情を持つ人たちは「長期的に認知症を発症するリスクが高かった」という結果を紹介。
しかし、この研究は性格と基礎疾患の証拠との間に直接的な因果関係を見つけることはできなかったと。
したがって、もしネガティブな感情を多く持っていたり、神経質であったりしても心配する必要はないとも。
一方、認知症リスクを減らすためにサリナス医師が推奨する行動は、
・定期的に運動する
・健康的な食事をする
・十分な睡眠をとる
・心と血管の健康を維持する
・社会的な支援システムを持つ
・精神的に刺激的な活動に参加する
・自転車などの活動中にヘルメットを着用する
ライフスタイルの改善が大切ですね。
12月24日に、認知症あんしん生活実践ケア研究会の第2期が開催されました。
自立支援介護学が基本とするケア「水分」「食事」「排便」「運動」が、さらに、注目される時代となるでしょうね。
結果として、対象とするご利用者様の認知症状の消失を達成し、多くの企業・法人様で、今月から、次のご利用者様の改善に挑戦しています。
この事実を、多くの皆様に知っていただきたいですね。
仏教の教えですが、「衣裏珠(えりじゅ)の譬え」という寓話をご存じですか。
「一人の男が友人の家で酔いつぶれ寝てしまう。男が眠っているあいだに友人は男の衣の裏地に何ものにも代えがたい宝を縫い付け、何も言わずに出ていく。目を覚ました男は何ごともなかったかのようにその家を出ると、真実の教えを求めて何年ものあいだ国々をさまよい歩く。何年か後に友人と再会したとき、男はぼろぼろになった衣に宝が隠されていたことを知る。」
介護業界の「衣裏珠(えりじゅ)の譬え」が「自立支援介護学」では。
2024年介護報酬改定「地域包括ケアシステムの深化・推進」では、認知症の方や単身高齢者、医療ニーズが高い中重度の高齢者を含め、質の高いケアマネジメントや必要なサービスが切れ目なく提供されるよう、地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な取組を推進と。
「認知症の対応力向上」のためのスキルは、介護に求められる重要なスキルとなりますね。
この研究会は、「科学的介護AtoZ研究会」と名称変更し、
さらに、多くの企業・法人の皆様に、その学びの場をご提供したいと
考えています。
ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。お待ちしています。
それでは、コマーシャルです!!
「PHJ科学的介護サミット2024 in FUKUOKA」開催決定
本気で科学的介護を導入した6法人の事例を特別公開!
実際にPHJが支援をした6法人の方に登壇いただき、その成果を共有するサミットを開催します。
このイベントは、未だ科学的介護を導入することに迷いがある経営者の皆様に、新たな視点を提供し、持続可能な経営と社会貢献の実現への一歩となることでしょう。
ご興味のある方は、下記LPをご覧いただき、ご参加をご検討ください!
-
ブログ2023.12.25
「他山の石」です!
いつもお世話になっております。
PHJの堀内です。
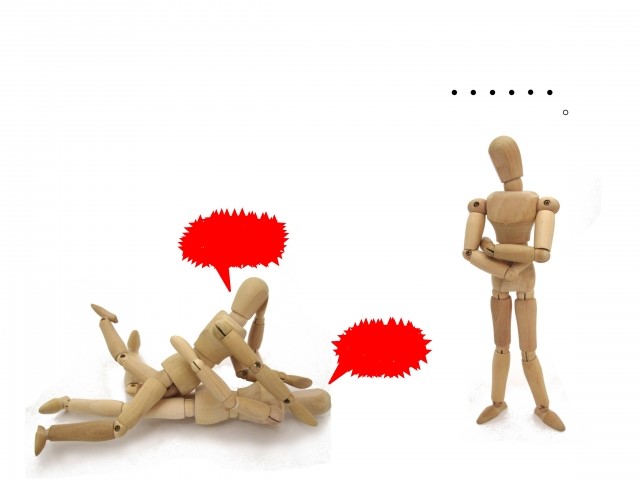
「ビッグモーターで買ったダイハツのタント乗ってて給油はエネオス使ってるんだけど、なんで今年になって不祥事フルセットになってんだよ」。
X(旧ツイッター)上の書き込みです。
「ビッグモーターに始まり、ダイハツの不正で終わる。今年の自動車業界は激動の1年」。
「2023年 企業やらかし案件、ビッグモーターとジャニーズのツートップで終わりと見せかけてこの年末ギリギリにダイハツが滑り込んで来たな」。
「じゃあビッグモーターで買ったダイハツが1番ヤバいってことやな」。
などとコメントが挙がったとか。
ダイハツ不正問題での第三者委員会による調査報告書を読みました。
「現場任せで管理職が管理しない態勢」
管理職が認証試験の実務や現場の状況に精通しておらず、また、報告や相談を行っても認証試験の担当者が抱える問題の解決が期待できない結果、現場の担当者レベルで問題を抱え込まざるを得ない状況が生じたことであると思われる。
「ブラックボックス化した職場環境(チェック体制の不備等)」
チェック体制が構築されていなかったことに加え、専門性の高さから属人化により衝突安全試験の領域が外部から目の届きにくいブラックボックス化した職場環境にあったからこそ不正行為が発生した側面かあり、こうした環境になければ、認証試験の担当者はそもそも不正に及ぶことはなかったと思われる。
「現場と管理職の断絶による通常のレポーティングラインの機能不全」
現場レベルでの問題は、本来、管理職を介した通常のレポーティングラインを通じて管理職や経営幹部まで情報が吸い上げられて経営レベルでの対応が検討されて然るべきである。
しかし、管理職が認証試験の実務や現場の状況に精通しておらず、報告や相談を行っても認証試験の担当者が抱える問題の解決が期待できない状況が生じていたことから、現場サイドから管理職に報告や相談ができずに現場任せの対応になっていた。
「ダイハツの開発部門の組織風土の問題」
・現場と管理職の縦方向の乖離に加え、部署間の横の連携やコミュニケーションも同様に不足していること
・「できて当たり前」の発想が強く、何か失敗があった場合には、部署や担当者に対する激しい叱責や非難が見られること
・全体的に人員不足の状態にあり、各従業員に余裕がなく自分の目の前の仕事をこなすことに精一杯であること
「自分や自工程さえよければよく、他人がどうであっても構わない」という自己中心的な風潮がある組織風土が、認証試験の担当者に対するプレッシャーや部門のブラックボックス化を促進し、リスク情報の経営層への伝達を滞らせる土壌となっていたと思われる。また、こうした組織風土の問題は必ずしも開発部門に限られるものではなく、ダイハツの全社的な組織風土、すなわち「社風」として深く根付いている可能性かおる。
報告書を読み込んだ人たちから、
「ブラック企業あるあるで、かつ身に覚えがありすぎて笑えん」。
「まさに、今のうちの会社」。
「心臓が痛い」。
と自身の勤める会社と比較し、人ごとではないととらえる声がネットに多く上がったとか。
中国最古の詩集「詩経」に由来する「他山の石」。
「他山石可以攻玉(他山の石以って玉を攻むべし)」
介護業界の皆様!
来年、「介護業界が激動の1年」と、ならないよう祈っています。
PHJが提唱する「PHJ-リーダーシップ・マネジメント・コミュニケーション・倫理教育メソッド【PHJ-LMCEメソッド】」には、組織風土改革の手法と「倫理」教育がプログラムされています。
今、手を打つべきです。
PHJがお手伝いさせていただきます。お気軽にご連絡ください。
それでは、コマーシャルです!!
「PHJ科学的介護サミット2024 in FUKUOKA」開催決定
本気で科学的介護を導入した6法人の事例を特別公開!
実際にPHJが支援をした6法人の方に登壇いただき、その成果を共有するサミットを開催します。
このイベントは、未だ科学的介護を導入することに迷いがある経営者の皆様に、新たな視点を提供し、持続可能な経営と社会貢献の実現への一歩となることでしょう。
ご興味のある方は、下記LPをご覧いただき、ご参加をご検討ください!
-
ブログ2023.12.22
昔:「椅子取りゲーム」、今:「人取りゲーム」
みなさん、お元気ですか?
経営者の、施設長の、管理者の皆様。
ポスト・ヒューマン・ジャパン株式会社(PHJ)の谷本です。

谷本が介護業界の中でコンサルティングのお仕事を始めた頃、時代は、「サービス付き高齢者向け住宅と地域包括ケアシステムが日本を救う!」的なムードでした。
多くの経営者は事業拡大意欲がたくましく、お金と建物を増大させるコンサルニーズが花盛りでもありました。
合言葉は、「椅子取りゲームに勝て!」だったのです。
特養の公募をとれ!サ高住×包括報酬サービスを掛け合わせろ!医療ケアを必要とする高齢者を集めろ!などなど・・・・・。
時代は変わり・・・・・・、今の合言葉は・・・・・・・。
「人取りゲームに勝て!」
皆様、いかがでしょうか?
「人取りゲーム」に勝つための、武器はお持ちでしょうか?
数年の間に、「人取りゲーム」に勝つ法人は、全国各地で、ゲリラ的に出現するでしょう。
その裏には、PHJのコンサルタントが控えています。
介護業界で、生き残るには、「黒田官兵衛」が必要なのです。
生き残りのための戦略参謀が必要な経営者の方、ご相談に乗ります。
では、また!
それでは、コマーシャルです!!
「PHJ科学的介護サミット2024 in FUKUOKA」開催決定
本気で科学的介護を導入した6法人の事例を特別公開!
実際にPHJが支援をした6法人の方に登壇いただき、その成果を共有するサミットを開催します。
このイベントは、未だ科学的介護を導入することに迷いがある経営者の皆様に、新たな視点を提供し、持続可能な経営と社会貢献の実現への一歩となることでしょう。
ご興味のある方は、下記LPをご覧いただき、ご参加をご検討ください!
https://semican.net/event/posthuman/noulhc.html
-
ブログ2023.12.21
学者の世界〜博士論文の作法と介護〜「思い」ではなく「ファクト(事実・結果)」
みなさん、お元気ですか?
経営者の、施設長の、管理者の皆様。
ポスト・ヒューマン・ジャパン株式会社(PHJ)の谷本です。
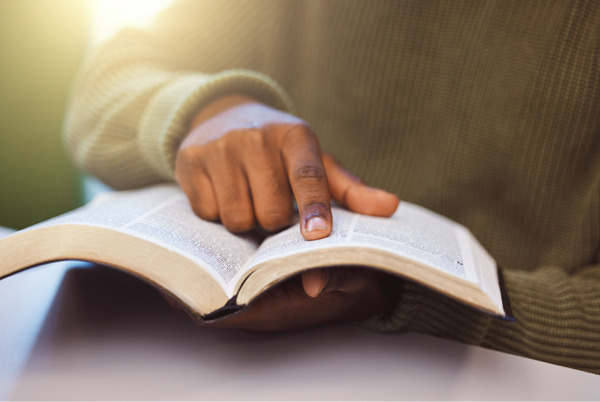
いわゆる「読み物」と「博士論文」の違い、ご存知ですか?
医学博士の「論文」とお医者様が書く「読み物」の違い、みたいなものです。
「論文」は研究前に大学等の倫理審査をパスしなければ研究を開始できません。
かつ「論文試問」という名の審査では、論文の内容を審査します。
その際、留意点として上がるのが、研究調査の「結果」「事実」に対して「考察」しなさい〜という流儀です。
学術論文の世界での作法は、「あなたの思いの吐露は、論文に値しない」です。
これが1流の世界です。
これを介護に応用して考えてみましょう。
「思いで介護を行う」「私の思う介護とは」・・・・・これは、3流です。
「利用者の身体状況」「利用者の精神状況」・・・・・という「結果」「ファクト(Fact)」に対して考察してケアを施すのが「科学的介護」であり、1流の世界観と言えるのではないか、ということです。
3流の世界には求人は集まりません。
人々はいつの時代も1流に憧れを抱き、やりがいと充実感を感じます。
当然、1流の世界には「負担」「負荷」が生じます。
それが何か?と採用面接では問いかけてください(心の中で?!)。
「科学的介護」なら新卒採用が可能です。
お手伝いさせていただきます。
では、また!
それでは、コマーシャルです!!
「PHJ科学的介護サミット2024 in FUKUOKA」開催決定
本気で科学的介護を導入した6法人の事例を特別公開!
実際にPHJが支援をした6法人の方に登壇いただき、その成果を共有するサミットを開催します。
このイベントは、未だ科学的介護を導入することに迷いがある経営者の皆様に、新たな視点を提供し、持続可能な経営と社会貢献の実現への一歩となることでしょう。
ご興味のある方は、下記LPをご覧いただき、ご参加をご検討ください!
https://semican.net/event/posthuman/noulhc.html
-
最近の投稿
- 人間の心とは・・・・・・。 2024/01/16
- 心根のいいヤツ! 2024/01/15
- 社会福祉法人は「営利を追求してはならない」?〜「社会福祉法人の財務目的:赤字経営は許されない理由」 2024/01/12
- 経営者と「行動」 2024/01/11
- 2024年介護報酬改定は、中継ぎ改定 2024/01/10
-
アーカイブ
