ブログ
ブログ|ポスト・ヒューマン・ジャパン株式会社(PHJ)
-
ブログ2024.01.16
人間の心とは・・・・・・。
いつもお世話になっております。
PHJの堀内です。

能登半島地震で、お亡くなりになられた方々に、心からお悔やみ申し上げます。
また、被災している方々に、心からお見舞い申し上げます。
厚労省が、昨年末、虐待についてのデータを、相次いで発表。
一つは、2022年度に都道府県・市町村が対応した障害者虐待の状況。
障害者福祉施設職員による虐待として通報されたのは4104件で、そのうち自治体が虐待と認めたのは956件、被害者は1352人。
いずれも過去最多を更新したと。
24年度の報酬改定では、虐待防止の取り組みが不十分な場合に減算する方針とか。
そして、2022年度に介護施設職員による高齢者虐待の状況。
856件(前年度比16%増)あり、虐待を受けた高齢者は1406人(3%増)で、いずれも過去最多となったと。
また、856件のうち2割超(182件)は過去にも虐待を起こしていたという。
厚労省は「要因の改善が不十分と考えられる。虐待防止の実効性を確保することが重要で、必要な方策を検討したい」と。
虐待があったのは特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、認知症グループホームの順に多く、虐待した職員1024人の8割が介護職。
内容は、身体的虐待が最多で、心理的虐待、介護放棄と続く。
全体の2割で身体拘束もあったとか。
虐待理由は、「教育・知識・介護技術の問題」「職員のストレス」「虐待を助長する組織風土」。
一方、相談・通報件数も2795件(17%増)で最多を更新。
厚労省は「職員研修の実施、相談窓口の周知などを通じて高齢者虐待に対する意識の高まり、虐待と認識されなかったケースの顕在化などが考えられる」と。
24年度から介護事業者に対し、虐待防止の委員会設置、研修会開催が完全義務化される。未措置の場合は基本報酬が減算されるという。
しかし、私は、厚労省の見解は、甘いと思います。
この数字は、氷山の一角では。
一方、連日、報道される被災地の報道。
その中で、避難所となっている各施設で、自らも被災しながら、懸命に支援をする医療・福祉の職員の方々の姿。
そこまで、人のために尽くすことができるとは。
本当に、感謝です。
人間の心とは、不思議ですね。
シェークスピアと並び称される、17世紀のイギリスの大詩人、ジョン・ミルトンの言葉。
「心というものは、それ自身一つの独自の世界なのだ。──地獄を天国に変え、天国を地獄に変えうるものなのだ」(『失楽園』平井正穂訳、岩波文庫)と。
先日、1月20日開催の「PHJ科学的介護サミット2024 in FUKUOKA」に、
ご参加される大尊敬する方から、このようなメールをいただきました。
【「科学的介護」における意義や重要度の認識がまだまだで、これから取り組んでいかないといけない事業所が沢山あります。またそれ以前に、倫理面の教育が必要不可欠です。】と。
その通りですね。
もっとも大切なのは、意識改革を実現する「教育」ですね。
PHJが提唱する「PHJ-リーダーシップ・マネジメント・コミュニケーション・倫理教育メソッド【PHJ-LMCEメソッド】」には、意識改革を実現する「倫理教育」がプログラムされています。
根本的な意識改革のための教育をと、お考えの皆様!
PHJがお手伝いさせていただきます。お気軽にご連絡ください。
それでは、コマーシャルです!!
障がい福祉サービス報酬改定経営戦略セミナー開催決定(参加無料)
会場参加定員50名Zoomオンライン参加定員100名
参入事業者の増大だけが話題になる障がい者・障がい児福祉の市場で生き残る方策とは?
放課後デイサービス、児童発達支援の専門性強化への戦略・戦術は万全か?
持続可能経営、サービスの質向上の方法を徹底解説
講師:ポスト・ヒューマン・ジャパン株式会社代表取締役社長 谷本正徳
開催日時:2024年1月26日(金)13時30分~15時30分
開催場所:北海道札幌市北区北7条西5丁目5-3
あいおいニッセイ同和損保株式会社 札幌千代田ビル11階会議室
主催:有限会社オフィスブレイン
共催:ポスト・ヒューマン・ジャパン株式会社
お申し込みは、下記お申込みフォームから
https://forms.gle/iH5c7va6hApLh5ro8
お申込みをお待ちしています。
-
ブログ2024.01.15
心根のいいヤツ!
いつもお世話になっております。
PHJの堀内です。

能登半島地震で、お亡くなりになられた方々に、心からお悔やみ申し上げます。
また、被災している方々に、心からお見舞い申し上げます。
『心根のいいヤツをとる』。
これは、
100回目を迎えた箱根駅伝。青山学院大学が2年ぶり7度目の総合優勝を果たしましたが、その原監督の言葉です。
「監督就任3年目のことでした。1年目、2年目と思うような成績を残せなかった私は、契約最終年の3年目、人間性を度外視してタイムが良いだけの選手をスカウトすることに決めました」
「原君、あんな選手をとってはいけない。部がダメになるぞ」との助言もあったとか。
その決断は最悪の結果に。
そして、
「表現力豊かで、勉強もしっかり取り組める心根のいい選手」という青学陸上競技部のスカウトの基準を確立できたとか。
原監督は、「自分のことしか考えられない人のことを私は、心根の悪いヤツと表現します。
それよりも、ほかの人と協調しながら行動できる心根のいいヤツをとるほうが、短期的な伸びは小さくても、長い目で見ると組織全体の力を伸ばすことにつながるのです」と。話は変わりますが、1月7日に、第3期認知症あんしん生活実践ケア研究会を開催し、その中で、1期生の体験を発表いただきました。
岡山県の株式会社かむら堂の管理者林田さんです。
対象としたご利用者様の認知症状消失状況、また、現在もお元気であるとの
報告。
そして、自立支援介護を組織全体で取り組んでいる状況を報告していただきました。
・共犯者を作る
・毎日続ける日の丸弁当
・最大限より最小限
初めは、一人から始まり、一緒に行動する仲間を作り、毎日、コミュニケーションをとって、価値感を
共有するなど、組織に定着させるまでのポイントをお話しいただきました。
現在は、独自に、ルールブックを作成して、価値感を共有しているとか。
このルールブックに示された価値感を、職員採用の時に確認するとも。
そうです。
「心根」の確認です。
研究会後、林田さんから頂いたメールを紹介します。
(林田さん、ごめんなさい。あまりにも感動しましたので紹介しちゃいました。)
【肝心の社長のお言葉を最後にお伝えさせていただくのを忘れておりました…。
緊張ばかりしていてはだめですね。
今回の資料作りにあたり、社長の思いを再確認させていただきました。
「何よりも、ご利用者様を元気にして地域で、在宅で、笑顔のある生活をしていただきたい。そのためには、良いと思ったことはとことん手を出してやってみる方がいい。結果が少しでも出るのであれば、取り入れていくのは当たり前。それが他社との差別化にもつながっていく。」
と話されていました。】
岡山県のかむら堂様は、「心根の良い」組織だと大感動です!
「トップは万卒のため死ぬ心根を持て」
経営の神様松下幸之助氏の名言です。
さて、皆様の組織の「心根」は、いかがでしょうか?
-
ブログ2024.01.12
社会福祉法人は「営利を追求してはならない」?〜「社会福祉法人の財務目的:赤字経営は許されない理由」
みなさん、お元気ですか?
経営者の、施設長の、管理者の皆様。
ポスト・ヒューマン・ジャパン株式会社(PHJ)の谷本です。
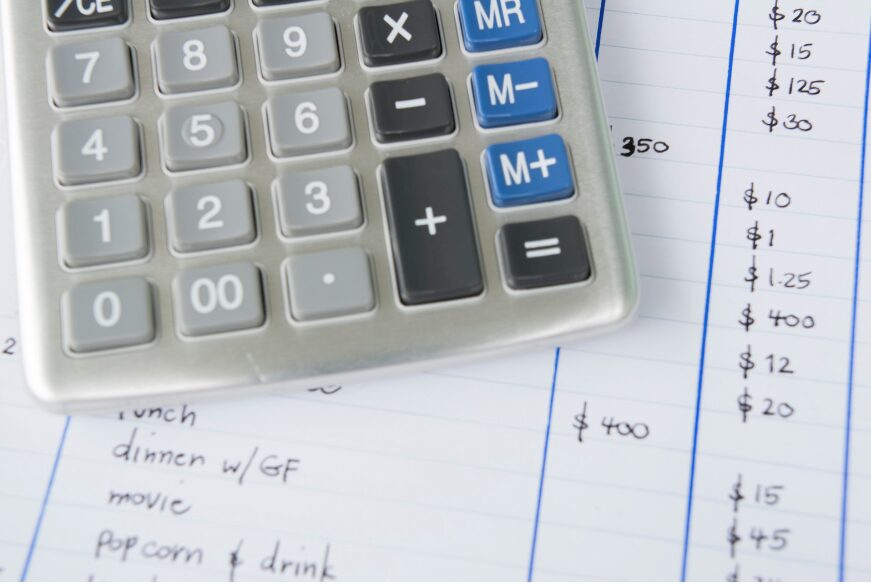
顧客の社会福祉法人の管理職から以下のご相談がありましたので、その回答を今回のメルマガに転用します。
「デイサービスの稼働率を向上させるために営業活動の促進を職員に促したところ
“社会福祉法人が利益を上げようとするのは法律違反になるから営業活動は行いたくない”と反発されています。どうしたら良いでしょうか?」
これについては当該職員の知識不足と歪曲の屁理屈ですので、正しい事実を確認します。
はじめに:社会福祉法人のミッションと誤解
社会福祉法人は、利益追求を目的としない非営利組織です。そのため、しばしば「利益を出す必要はない」とか「赤字であっても問題ない」という誤解が生じがちです。しかし、この理解は組織の持続可能性と効果的なサービス提供にとって重大な誤りです。
利益とは「余剰」のこと
まず、非営利とは利益を追求しないことを意味しますが、これは「余剰」を生み出してはならないという意味ではありません。利益(または余剰)は、組織が健全に運営され、将来にわたってサービスを持続的に提供できるよう保証するために必要です。
赤字の継続はサービスの質を低下させる
赤字が続くと、社会福祉法人は必要な資源(人員、設備、プログラム)を維持できなくなります。この結果、提供するサービスの質が低下し、最終的には利用者に悪影響を及ぼす可能性があります。
株式会社と社会福祉法人の根本的な違い
株式会社は、事業活動を通じて剰余金を生み出し、その利益を株主に分配することで株主価値を最大化することを目的としています。
一方で、社会福祉法人は利益の最大化を目的としませんが、それは赤字経営が許されることを意味しません。
社会福祉法人の使命:剰余金の社会的活用
社会福祉法人の存在理由は、社会的使命の遂行にあります。剰余金を生み出すことは、この使命を効果的に果たすための手段です。
剰余金は、制度の狭間に落ちがちな国民を迅速に救うため、また、不特定かつ多数の国民の利益を増進するために活用されます。
赤字経営の危険性
赤字が続けば、社会福祉法人はその社会的使命を果たすための資金を失います。これにより、社会に対する責任を果たす能力が低下し、最終的には組織の存続自体が危うくなります。
赤字経営は、社会福祉法人にとって持続可能な運営を妨げ、社会的価値の創出を阻害します。
財務健全性の重要性
社会福祉法人は、持続可能な運営を実現するために、財務の健全性を確保する必要があります。これには、効率的な資源管理、費用対効果の高いサービス提供、そして必要に応じて剰余金の生産が含まれます。
剰余金は再投資され、サービスの質の向上、新たなプログラムの開発、組織の成長に寄与します。
結論
社会福祉法人は、株式会社とは異なる目的を持っていますが、その運営においては財務の健全性が極めて重要です。剰余金を生み出し、それを社会的使命の遂行に活用することが、これらの組織の基本的な責務であり、赤字経営はその責任を果たすことを妨げます。
よって、社会福祉法人が利益を追求するのは法律違反という論調は全く事実に反した錯覚ということになります。
フォームの終わり
では、また!
-
ブログ2024.01.11
経営者と「行動」
みなさん、お元気ですか?
経営者の、施設長の、管理者の皆様。
ポスト・ヒューマン・ジャパン株式会社(PHJ)の谷本です。

私たちPHJは、お客様である社会福祉法人様の組織マネジメント再生のお手伝いをメインの仕事としております。
さて、マネジメントとは何なのか?
P.F.ドラッカーは、マネジメントの語源と意味についての洞察について、マネジメントが「手を使って」という意味のイタリア語「maneggiare」から派生した言葉であると説明しています。
この言葉は、もともと馬を訓練することを指していました。
ドラッカーは、この語源を引用して、マネジメントの本質は「リソースを使いこなし、生産性を高め、組織の目標を達成すること」であると説いています。
シンプルにいうと、「人材をどうにかこうにか使いこなして、アウトカムを出す」ための行為をマネジメントというのだということです。
馬の手綱を自分の手を使って、馬を走らせるイメージでしょうか。
彼によれば、マネジメントとは単に人をコントロールすることではなく、リソース(人的資源を含む)を効率的かつ効果的に活用し、目的を達成するためのプロセスであるとされています。
要するに、マネジメントの役割を
・「目標の設定」
・「組織化」
・「モチベーションとコミュニケーション」
・「測定」
・「人材の開発」
と考えていたわけです。
確かに、これらの要素は、組織が成功するためには不可欠なものといえます。
これからの介護業界は、あるいはそれぞれの社会福祉法人は、株式会社は、医療法人は・・・・。
経営側として・・・・・・。
・どのような目標を設定するのが最適解なのでしょうか?
・組織をどのように再生すべきなのでしょうか?本当に“現状のまま“で持続可能なのでしょうか?
・管理職や一般職が“モチベーション”を高めるためには、“コミュニケーション”の質を高めるために、どのようなスキルを身につけるべきなのでしょうか?
・人事考課制度は、客観性があるでしょうか?人事の登用と降格はアウトカム評価になっているでしょうか?(ちなみに長く勤めているからとか、創立期から頑張ってくれているから・・・はプロセス評価となり、日本企業の凋落の要因とされています)
・人材への教育投資に総費用の1〜2%をしっかり充当しているでしょうか?
あいだみつをの言葉を紹介します。
“花を支える枝 枝を支える幹 幹を支える根 根はみえねんだなぁ”
経営者が、当然に、“根”です。経営者がどのような“行動”をするのか?
これが持続可能な経営の全てです。
フォームの始まり
フォームの終わり
では、また!
-
ブログ2024.01.10
2024年介護報酬改定は、中継ぎ改定
厳しい、新年の日本となりました。
みなさん、お元気ですか?
経営者の、施設長の、管理者の皆様。
ポスト・ヒューマン・ジャパン株式会社(PHJ)の谷本です。

1月〜2月は、私、2024年介護報酬改定セミナーの講師のオファーで目白押しで、全国様々な地域にお邪魔します。
今回の改定のご感想、皆様、いかがでしょうか?
こんな声が聞こえてきました。
「・・・今回、意外に【科学的介護】について、それほど大袈裟な改定内容ではないので、科学的介護教育コンサル、やはり見送ります・・・・。」
はっきり言います。
この経営判断は、変更することをお勧めします。
「科学的介護」を、あなたの経営する介護施設で、実現するのは、(入居者の廃用症候群からの回復や認知症BPSD消失というアウトカム(成果)を出せるという意味の「科学的介護」です)、簡単ではありません。
教育に時間がかかるだけではなく、従前の、あなたの経営する組織のウィークポイントを消し、組織のマネジメントとリーダーシップとコミュニケーション(上司と部下の)の質を、強化、強靭にしなければ、できないのです。
この取り組みには、最低1000日間かかるとPHJはとらえています。
3年間くらいですね。
それで、ようやくスタートに立つ程度かもしれません。
意識と無意識に染みついた、現場迎合主義と、変革する。
意識と無意識に刻まれた、エイジズム(高齢者差別)を、転換する。
など、理事長が未だかつて経験のない取り組みとなります。
ちなみに理事長が年中、「科学的介護」の旗を振り続けなければならないこと、現場に任せていたらフェイドアウトしていくことも一言加えておきます。
ダイエットのリバウンドみたいなものです。
なので、取り組みは、「今」が好機到来、です。
では、また!
-
最近の投稿
- 人間の心とは・・・・・・。 2024/01/16
- 心根のいいヤツ! 2024/01/15
- 社会福祉法人は「営利を追求してはならない」?〜「社会福祉法人の財務目的:赤字経営は許されない理由」 2024/01/12
- 経営者と「行動」 2024/01/11
- 2024年介護報酬改定は、中継ぎ改定 2024/01/10
-
アーカイブ
